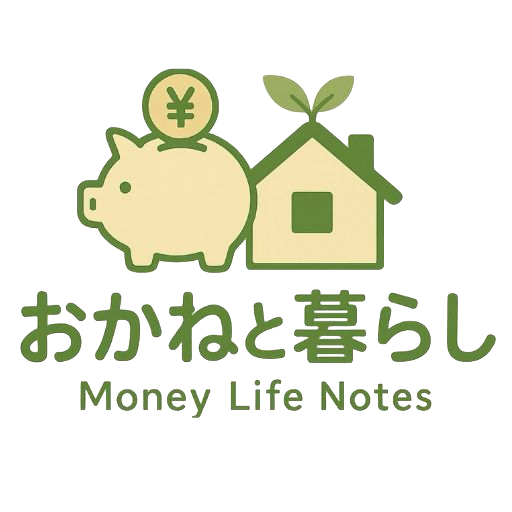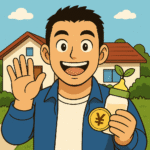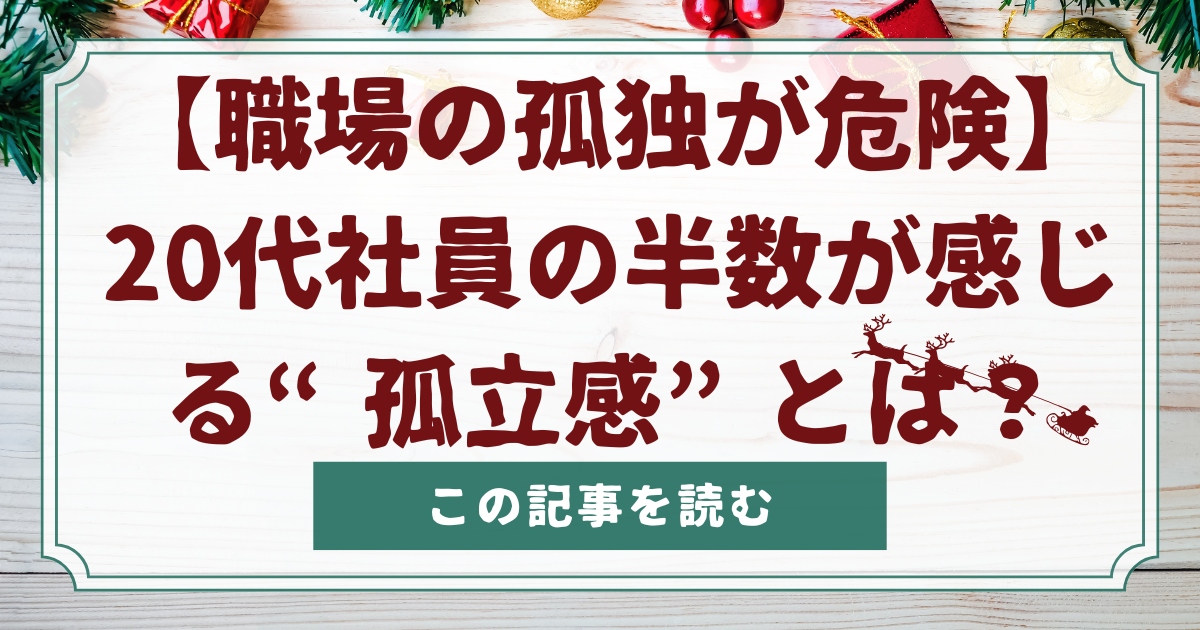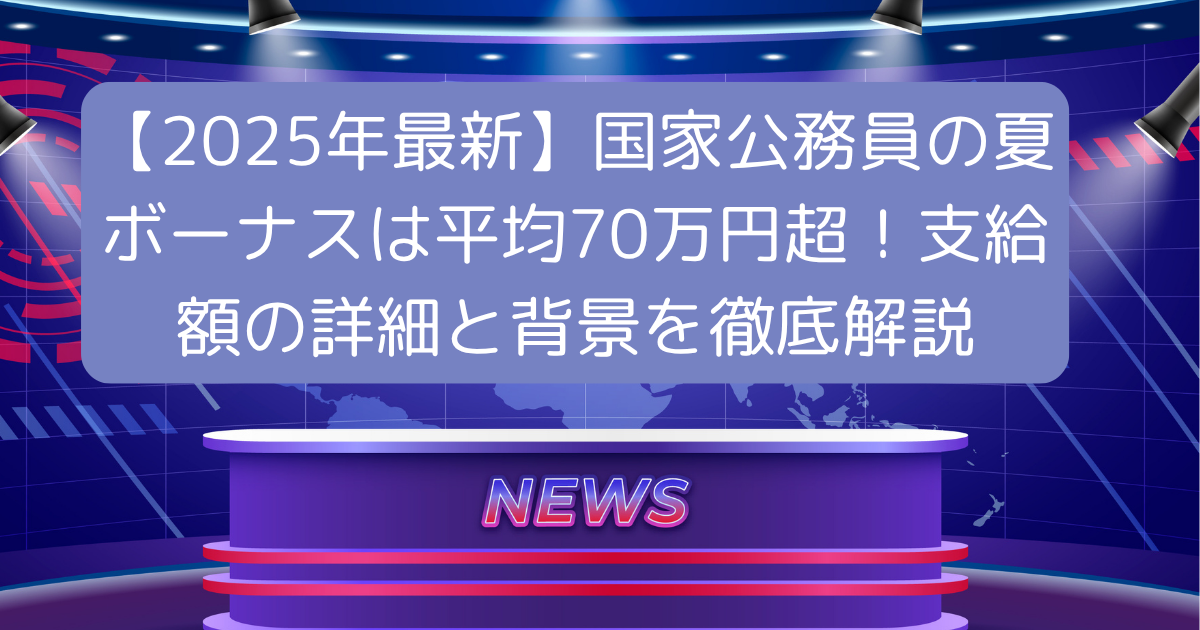【職場のグレーゾーン・ハラスメント】どうする?「平均的な労働者の感じ方」で判断される現実
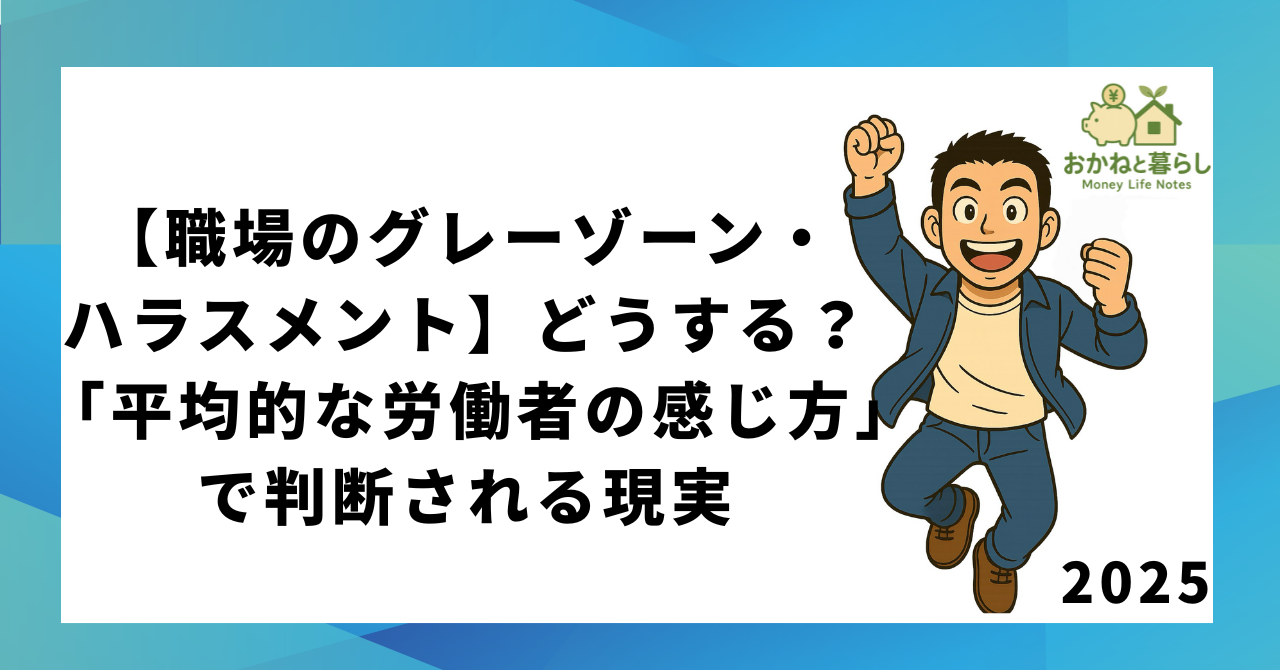
こんにちは、トシです。
今回はYahoo!ニュースで取り上げられていた、舟木彩乃さんの記事
「職場のグレーゾーンハラスメントどうする?『平均的な労働者の感じ方』とは」
について、わかりやすく解説・考察してみます。
■「グレーゾーン・ハラスメント」とは?
最近、パワハラやセクハラといったハラスメント問題に対する関心が高まる一方で、「これはハラスメントなのか、そうじゃないのか」と線引きが難しい場面が増えています。これがいわゆるグレーゾーン・ハラスメントです。
たとえば──
- 上司が部下に「もっと努力しなよ」と言う
- 飲み会で「空気を読んで参加しろ」と言う
- 休憩中の私語が多いと注意される
こうしたケース、受け取り方次第で「ハラスメント」とも「正当な指導」とも解釈できてしまいますよね。
■判断基準は「平均的な労働者の感じ方」
舟木さんの記事でも触れられている通り、裁判や法的な判断において重要視されるのは「受け手の主観」ではありません。
代わりに重視されるのは──
「平均的な労働者がどう感じるか」
つまり、受け手本人が不快だと感じたかどうかではなく、客観的に見て“平均的な人”ならどう感じるかが、判断の基準になるということです。
これは非常に重要なポイントです。
■主観と客観のギャップが起こす問題
たとえば、新人社員が上司のちょっとした指摘に対して「自分は攻撃された」と受け取ってしまった場合でも、その発言が社会通念上、普通の指導の範囲内であればハラスメントとは認定されません。
逆に、発言する側が「冗談のつもり」や「愛のムチ」だったとしても、平均的な感覚からして明らかに不快な表現や言動であれば、ハラスメントと判断されることもあります。
つまり、「自分がどう思ったか」だけでは、通用しない現実があるのです。
■グレーゾーンをどう乗り越えるか?
職場での人間関係は、どうしても曖昧さが付きまといます。その中で、次のような姿勢が求められます。
▼加害者にならないためには
- 冗談でも相手を貶す発言は避ける
- 指導は事実ベースで、感情を排して行う
- 日頃から信頼関係を築いておく
▼被害を感じた側は
- 感情だけで判断せず、まずは信頼できる第三者に相談
- 自分の感じ方が極端でないか、一度客観視してみる
- 職場の相談窓口や外部機関(労基署など)も活用
■トシの考察:「個の感性」と「組織の常識」の間で
私自身、これまでいくつかの職場を経験してきた中で、「これ、ちょっと言いすぎじゃない?」という場面や、「自分が傷ついても、他の人は気にしてなかった」なんて経験もありました。
だからこそ、「平均的な労働者の感じ方」という考え方は、ある種のフェアさと、ある種の冷酷さを持ち合わせていると感じます。
- 多様性を尊重するあまり、言いたいことが言えなくなる
- でも言いたい放題では、誰かが必ず傷つく
結局は、相手との信頼関係があるかどうかが一番のカギではないでしょうか。
■まとめ:職場のハラスメントは「グレー」でも無視できない
ハラスメントかどうかの判断は、「受け手の主観」ではなく「平均的な労働者の感じ方」で判断されます。だからこそ、発言する側にも、受ける側にも一定の客観性とコミュニケーション力が求められる時代になってきました。
職場の空気を健全に保つためには、日頃の小さな気配りと相手を尊重する姿勢が、グレーな関係を透明にしてくれるはずです。
▶あなたは、職場での「これ、グレーかも?」という経験、ありますか?
コメントや感想、お待ちしています!